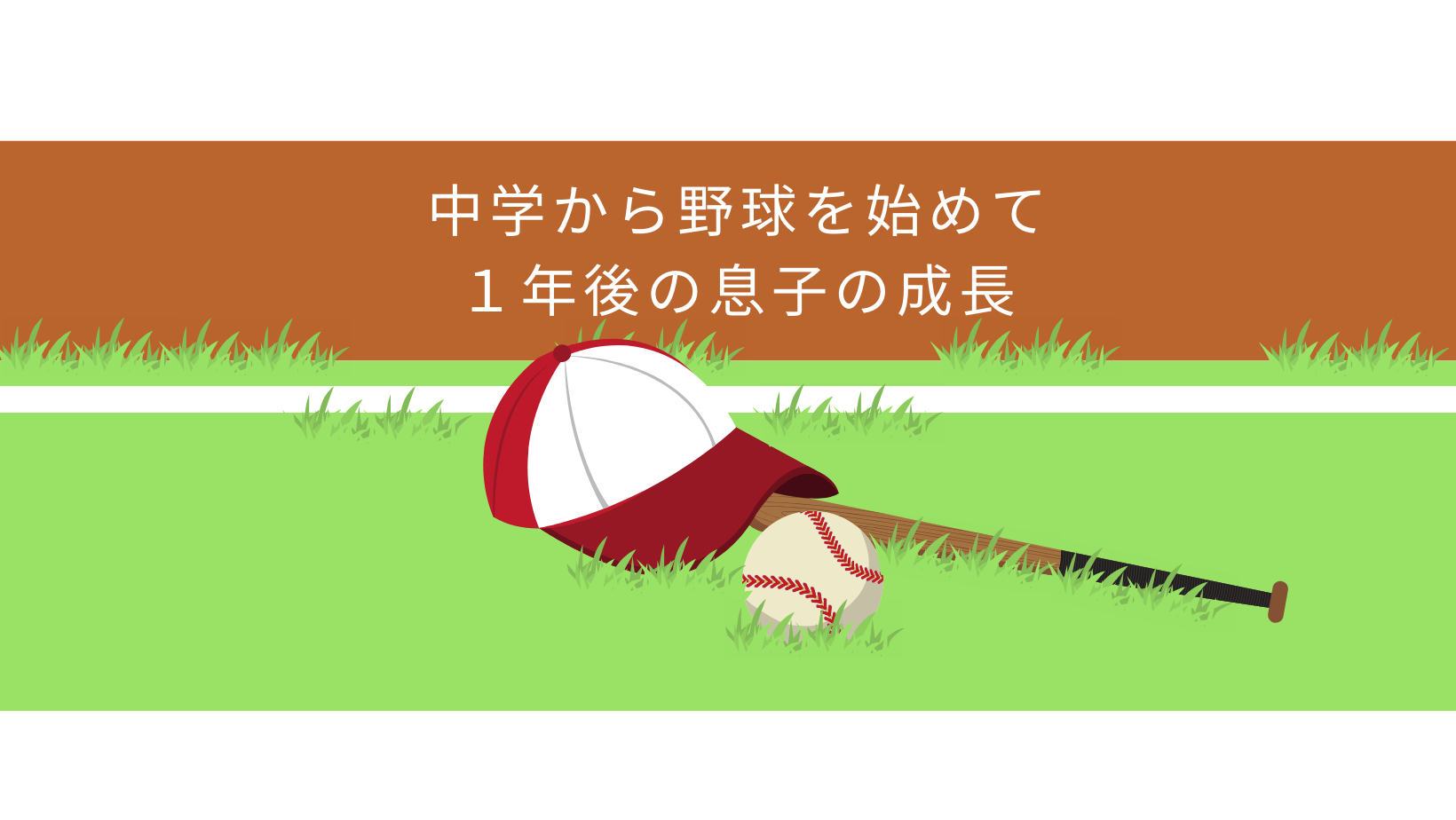小学4年生になった娘の成長と親が気になる悩みを解決!実践的なアドバイスと心配事の対策法

このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
こんにちは。かおです。
子供はあっという間に成長していきますよね。
我が家の息子も娘も成長が目まぐるしくて、対応に困る事がしばしばあります。
今回は小学4年生になった娘が成長したこと、成長に伴い今後の課題や考えた対処法について情報を共有させて頂きます。
小学3年生から4年生になった娘が成長したところ

学習面について娘が成長したことは、家庭学習の習慣が定着した事です。
そのため、宿題や学校で間違えた問題を私や主人、兄に質問して教えてもらうことができるようになりました。
塾の宿題や学校の宿題、パット学習を毎日繰り返すことで、家庭学習習慣が定着しました。
友人関係は4年生になりクラスが変わったことで新らしい友達と遊ぶようになりました。
民間の学童を辞めたことで、小学校が4時間や5時間授業後に外で友達と遊ぶことが増えました。
習い事の時間になると帰宅し、その後習い事へ出かけることもできます。
時間管理もできるようになりました。
習い事を辞めたいということもなくなりました。
ヒップホップダンスや体操教室や塾も友達がいることで楽しく通うことができています。
その中で友達とのトラブルがあった話は今のところ耳に入っていません。
しかし、心の成長と共に女の子は仲間外れや言葉遣い、文章の問題からSNS上でトラブルになったりすることがあります。
親子の関係も以前より対応がそっけなくなった印象です。
そこで、小学四年生の子育ての悩みを考えていきます。
親が気にしている悩み
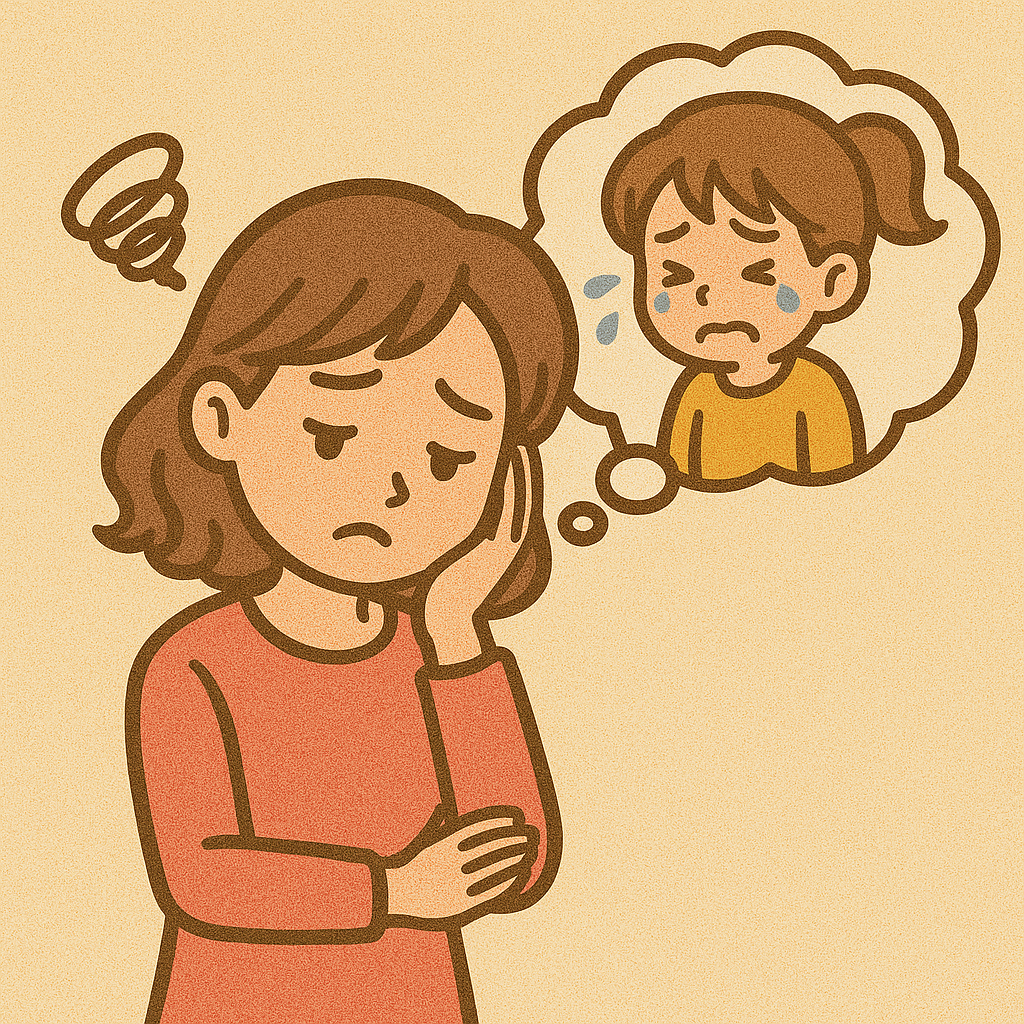
小学4年生になると高学年の仲間入りになるため、学力や友達関係等様々な不安が頭を過ぎります。
早い子は反抗期にもなってくるため、なかなか親に話してくれないことも多くなってきます。
そこで色々と私も不安に思っている悩みを挙げていきます。
1. 学業の進捗と成績

娘は今のところ家庭学習の習慣はありますが、以下の事が悩みです。
算数(特に分数や割り算)でつまずく
算数に関しては現在割り算を何度も解いて克服する作戦をやっています。
パット学習や塾で取り組み、学校でも解けるようになりました。
次に問題になったのは、角度の問題です。
娘は三角形の角度を求める問題につまずき、学校の宿題の中で私や兄に何回も質問し、娘本人のペースでゆっくり理解できるように説明しました。
はじめは分度器を使用し、実際に角度を測定しながら、計算して求めていきました。
何回も問題を解いていると、パターンがわかってきたのか、理解できるようになりました。
最初は分からなかったことも、人に質問して教えてもらったり、何回も解くことで解き方を覚えることで自信がついてきました。
今後も質問があれば根気強く教えていきます。
国語の読解力の伸び悩み
国語に関しては、漢字は覚えるのが得意なようで問題ないですが、読解については苦手です。
読書や音読を通じて、たくさん本を読んでその感想をアウトプットすることが良い方法と考え、娘が読んだ本の内容を娘の言葉で教えてもらったりしています。
すると嬉しそうに娘は本の内容を教えてくれるので、割と良い方法です。
話を聞いていると、きちんと理解して読んでいるなと思う部分もあれば、内容がぼんやりしている説明の仕方もあり、あまり理解できなかったんだなと感じることがあります。
あまりできていなかった内容のお話については、更に深堀してもらうよう話し、もう一度読んでみることをお勧めいたします。
こうすることで娘は学校のテストも悪い点数を取らずに済んでいます。
2. 友達関係や学校生活
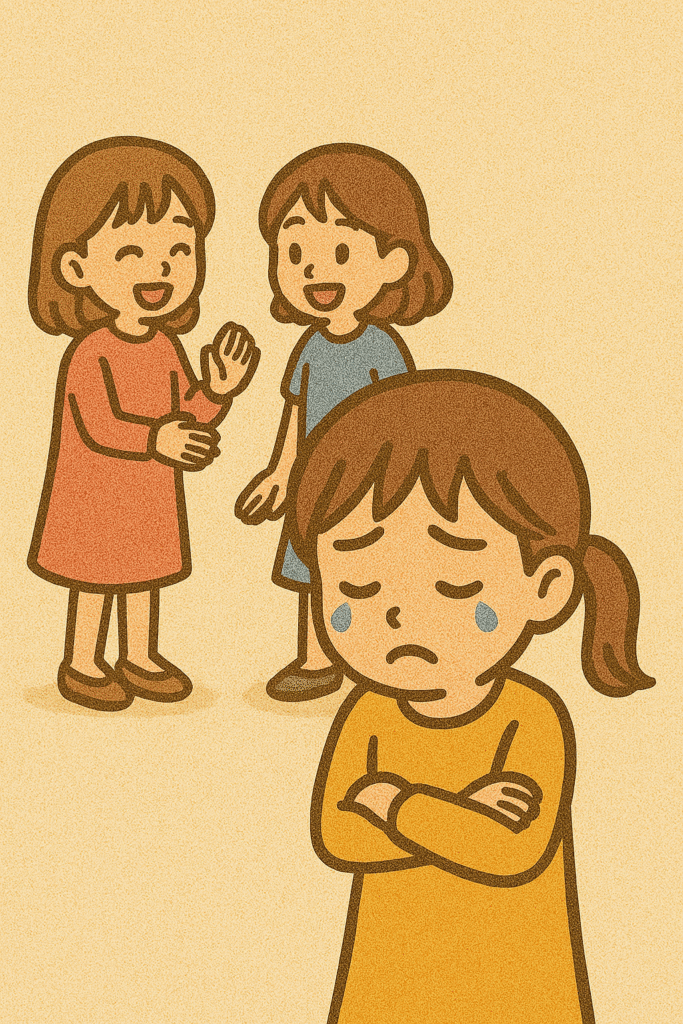
グループ内でのトラブルや仲間外れ
友達とのトラブルやコミュニケーションの悩みが小学四年生になるとあります。
娘は幸いお友達に恵まれていて、お友達とのトラブルが起きている話を今のところ聞いていません。
しかし、突然トラブルに巻き込まれる可能性があります。
落ち込んだ様子を見かけたり、お友達からトラブルの話を耳にした時は、本人が教えてくれるまで待ちちます。
そして親に話したくなった時に娘の言葉で話してもらい、思いに寄り添っていこうと考えています。
言葉づかいやSNSトラブルの兆し
よく仲の良い友達とLINEでトークで文字や絵文字打ったりやLINE電話をしてコミュニケーションをとっています。
月に一回くらいのペースでLINEのトークをチェックしています。
言葉が足りず、上手く思いが伝わっていない場面もしばしばあります。
上手く伝わらないときは、電話をして会話して思いを伝えることが今のところできています。
文字だけだと思いやニュアンスが伝わりづらいときが大人でもあります。
その場その場で娘本人に、この文章だと勘違いされることもあるよ等、実際のLINEの文章を一緒にみて、どんな文章だとお友達に伝わりやすいか、一緒に考えたりします。
大人も子供も、一緒にSNSのマナーや人に伝わる文章を考えあっていけると一緒に成長できますね。
友達との距離感がうまく取れない
子供が学校で楽しんでいるか不安になる瞬間も時にはありますよね。
娘が楽しかったことは積極的に話してくれますが、疲れていると話さないこともあるため、今日は小学校楽しくなかったのかな?と思うこともあります。
小学四年生の学校生活や友達関係は面談の時に担任の先生に聞いてみるのも一つの手です。
私はよく小学校の個人面談で、自宅で聞いている中の良いお友達のはなしをし、担任の先生に本当にそうなのか?と裏をとるような質問をします。
たいてい合っているのですが、家で話を聞いている事より更に多くの友達と交流していることに面談で気づけました。
娘は周りの空気を読むのが上手いので、友達との距離感は今のところ上手くとれています。
上手くお友達と距離感がつかめなかったりなどのお悩みがありましたら、是非一緒に出掛けたりして色々な方とお話をする機会を作ることをお勧めします。
色々な場所に行ってコミュニティを作ることで、学校と家以外の居場所を作ることも子供だけでなく親も大切です。
色々な居場所を作ることで、考えや行動が偏らずに視野を広げることにもつながるからです。
私は娘には学校だけでなく、習い事各種や校外のコミュニティーにも参加したり、兄の中学野球部の親子さん達とも交流する場に娘を連れて行ったりします。
娘も兄の野球部の親子さんとコミュニケーションをとったり、習い事のお友達と遊んだりすることで気持ちがリフレッシュできています。
人に会って人に学ぶ。
とても素敵なことです。
3. 身体の成長と健康
反抗的な言動が増えてきた
仕事から帰宅後に宿題をやったかと尋ねると、「今やろうとしたところ。」とか、そろそろお風呂に入ってきたらと声をかけると、「あと15分後に入る。」等、ああ言えばこう言う状態になります。
なかなか一筋縄ではいかず、娘は自分が決めた時間に実行したいタイプです。
私や主人が色々勧めても、必ず自分の考えに沿って行動するので、お勧めはするけれど基本見守ります。
年々、帰ってくる言葉に鋭いとげがあることが多くなってきました。
心の成長だと思い、見守ります。
体の変化(第二次性徴)への戸惑い
3年生から4年生にかけて娘は身長が6cm伸びていました。
すでに4年生の5月時点で身長が146cm。
体重は29Kgとかなりやせ型でイマドキの手足長い系の子です(笑)。
乳腺が発達し始めているため、そろそろ生理の事を教えてあげなければいけません。
今後第二次性徴のお話を少しずつしていく予定です。
日常生活はよく食べ、よく寝ています。
6時半に起床し、21時半から22時には就寝します。
健康管理とし生活リズムは崩さないように心がけています。
感情の起伏が激しくなる
娘は時々突然イライラしていることがあり、勉強中などに、「何でこの問題意味わかんないよ。」とか大きな声で怒りながら言っている時があります。
そんな時は娘の隣へ座り、どこが具体的にわからない事なのか確認したり、問題を一緒に音読して、問題の内容を一緒に考えながら解いていきます。
友達関係等上手くいっていなかったり、ストレスがあったり、体調が悪かったり等、感情の起伏が激しくなる理由は何かしらあるので、しっかり子供たちを観察しておくことをお勧めします。
4. 心の成長と自己肯定感
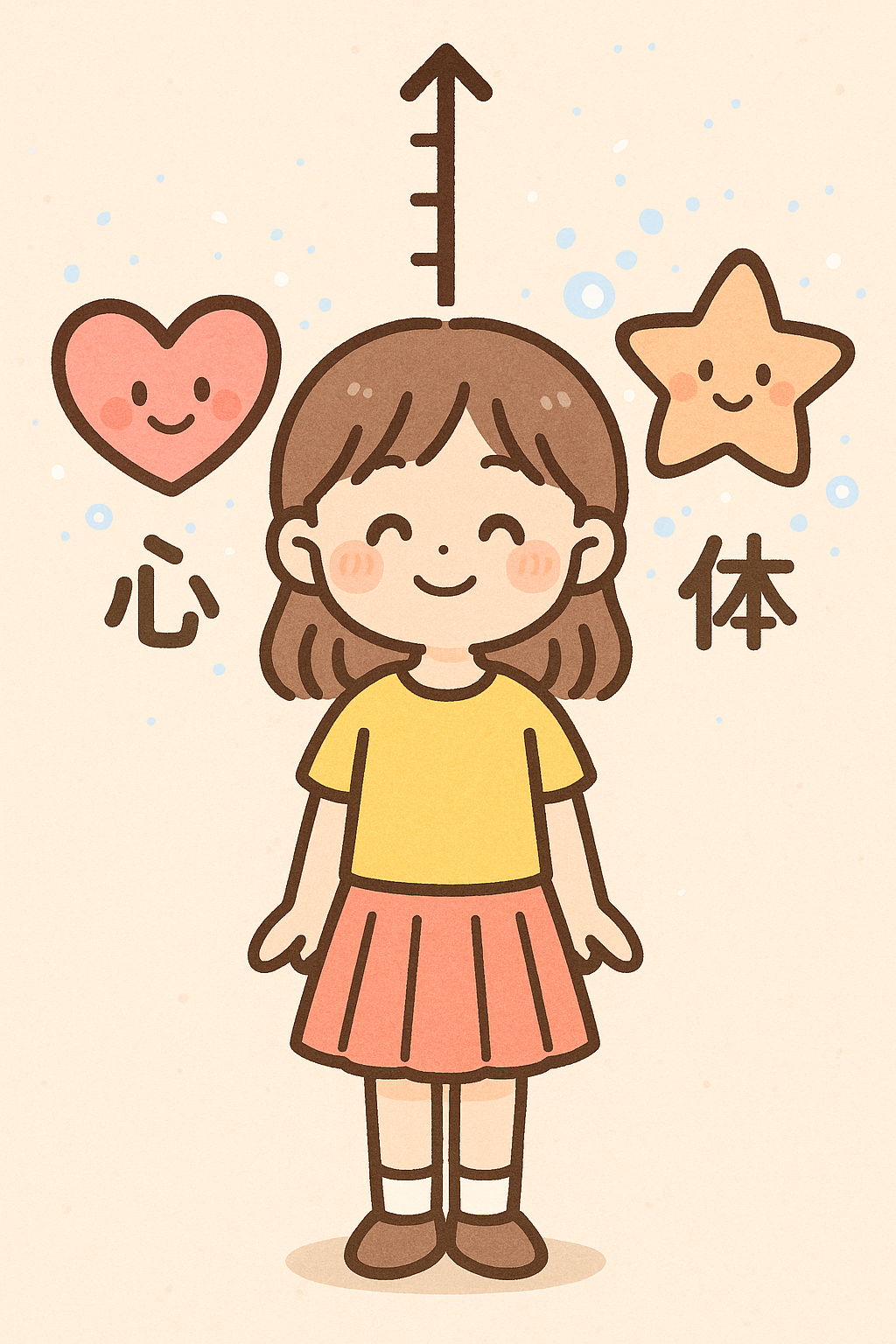
習い事が多く、時間に追われる生活
娘は平日毎日習い事をしています。
月曜日は塾(算数と国語)
火曜日は体操教室
水曜日はオンライン塾(コミュニケーション)
木曜日はHIPHOPダンス
金曜日は塾(算数と国語)
これに加えて、自宅でタブレット学習をしています。
時々辞めたいという時がありますが、今のところは継続しています。
「やめたい」と言い出すことへの対応
習い事を時々辞めたいと言い出すときがあります。
その理由は、自由な時間が欲しい!というものです。
習い事の時間以外は家でYouTubeを見ていたり、お絵描きをしていたり、工作をしていたり、友達と遊んでいたり等、色々行動できています。
十分自由な時間はありますよね、ということを伝えると娘はいつも納得しました(笑)
この繰り返しですよね(笑)
運動系の習い事は、体操教室とHIPHOPダンスを習っています。
体操教室はクラスがどんどん上がって上級クラスでやっているのですが、HIPHOPはなかなか下すが上がらないため、達成感がないときがあるようです。
しかし、空き時間があると踊り出すくらいダンスが大好きなので、今度ダンステストがあるためしっかり自主練習をして上のクラスへ上れるように頑張っていただきたいです(笑)。
やりたいことと向いていることのギャップ
大人も同じことが言えるのですが、やりたいことと向いている事のギャップがあります。
ギャップを知るためには、なんでもやってみないとわかりません。
私は基本的に娘がやりたいといった事は挑戦させていくようにしています。
やる気スイッチが入ったときがやりたいこと、向いてることを発見できるチャンスです。
どんどんやりたいことをやってみて、自分に合わないなと思えば辞めても良いし、続けたいなと娘本人が思えば続ければよいとしています。
どんどん色々なことにチャレンジして、自分の好き、得意を増やしてもらいたいです。
親離れが始まり、会話が減る
以前よりも娘との会話が減ってきたと感じます。
子供達の中で、親には内緒ねという友達との約束があるからです。
以前はなんでもかんでも小学校の情報やお友達の事も話してくれましたが、現在は少なくなりました。
お友達のうちに遊びに行くことも増え、遊びに行った先で楽しんでご機嫌で帰宅してきます。
しかし、具体的にどんな遊びをしたかはたくさん教えてくれることが無くなり、「一緒に学校の宿題をした。」とか、「塾ごっこをした。」等遊んだことを1つしか教えてくれなくなりました。
親の言うことを素直に聞かない
アドバイスをするときに、こういう風にやってみたらと伝えると、素直にすぐやってみる時もありますが、後でやるとか私はやりたくないとか色々な理由をつけてやらないこともあります。
成長の過程だと思い、素直に聞かないときは「そうなんだ。」と言って流します。
「自分でやる」と言いながら放置することが増える。
花を種から育てると宣言し、花の種を植えたことがあります。
毎日水をやると宣言していましたが、3日坊主でした。
芽は出ましたが、しわしわに枯れた芽を見て、「枯れちゃったね(笑)。」
と水を上げ忘れたことに対し、自分が忘れたからそだたなかったのか………。と反省していました。
植物が育たなかった理由が分かれば良しとしました。
その後なんでも自分でやるという宣言は聞かなくなりました(笑)
有言実行するというハードルを上げてしまったかもしれません。
でもむやみやたらに何でもやると宣言してやらずに放置するということはしなくなったので、成長したのかなと感じました。
小学4年生の問題、悩みの中で、自己肯定感を高めるためにはやはり本人がやりたいと思ったことをやらせてあげることが大事なのかなと感じました。
人の命に係わる事や迷惑になる事、事故につながる事以外は注意しながらどんどんやらせてあげることをおすすめします。
母親に自分がやりたいことを応援してもらえたことで、自己肯定感を高めることに繋がりますし、自信も持てます。
自己肯定感を高めることができれば、自分で考えて行動できるようになります。
心も成長しながら、自己肯定感が上がれば色々なことを自分で出来るようになっていきます。
各悩みを解決する具体的な方法

学業・勉強サポートの方法
親としてできる勉強サポート法
一緒に勉強を見てあげることです。
本人が分からないところを母親に質問しやすい環境を作ってあげることが大切です。
質問に対してもすぐに答えを言わずに、本人が答えを導き出せるように関わっていくことがポイントです。
例えば漢字の読み方が分からないから教えてと言われたら、漢字辞典や国語辞典で一緒に調べることを私は繰り返しています。
すると最近は漢字の読み方に対する質問が減り、自分で漢字の読み方を辞書で調べるようになりました。
勉強のやり方を一緒に学べるとよいですね。
そのためにも子供が親に質問できる環境がとても大切です。
子供とのコミュニケーションの場をたくさん設けてください。
ゲーム感覚で学べるアプリや教材の紹介
ゲーム感覚で学べることも大事です。
その中でタブレット学習が娘には有効でした。
下記のタブレット学習をよろしければ参考にされてください。
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3T6H7U+2JORXU+3OR6+6JZDE
友達関係のサポート
子供が友達と楽しく過ごすためのコミュニケーション方法
子供同士で楽しくコミュニケーションをとる方法の一つとして、お友達を自宅に遊びに来てもらうのも一つの方法です。
親の目もありますし、やってはいけない事をやっていたら注意すればよいです。
普段のお友達との会話も聞くことができます。
お友達に直接お話しすることもできます。
お友達からの学校や自宅の情報を聞くのも、違った意見があり面白いです。
本人も自宅だと安心して過ごせます。
トラブル解決法と親の関わり方
トラブル時には親子で一緒に考えます。
なぜトラブルになってしまったのか?
こういう時にはこういう風に行動するという改善、解決方法を考えたりできます。
お友達の事を考えながら言葉を選んだり、行動したりすることを学んでもらえれば良しと考えています。
自分がやられて嫌なことはしない、言わないということを頭に入れて行動するようにいつも話しています。
健康管理のアドバイス

成長に必要な栄養素や食事のコツはやはり成長期の必要項目はタンパク質摂取ですね!
肉、魚、大豆製品など、しっかり食べれるよう工夫しています。
おやつにも娘はビーフジャーキーを食べたり、牛乳を飲んだりしています。
娘は緑の野菜が苦手ですが、どのほかの野菜は少しづつではありますが、食べることができます。
しっかりバランスの取れた食事をして食べて大きくなってほしいですね。
運動習慣の作り方のポイントとしては、本人が好きな遊びをやることです。
娘はダンスが好きなので、習い事としてヒップホップダンスと体操教室を習っています。
週に1回いでもよいから、継続して今年で4年目になります。
何事も継続すれば上手になります。
上手になれば自身がついてきますし、自己肯定感も上がってきます。
歩くだけでも大丈夫です!
運動習慣を作ることは、大人になってからも生活習慣病の予防にもつながります。
たくさん体を動かしてもらい、たくさんご飯を食べて、寝てスクスクと成長してもらいたいです。