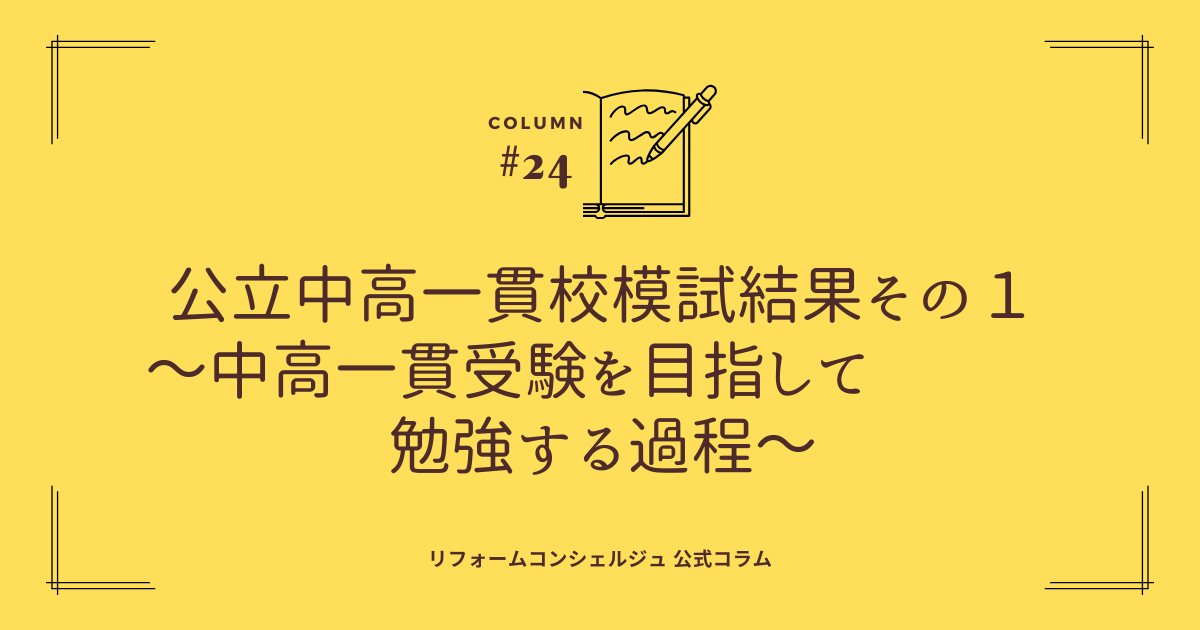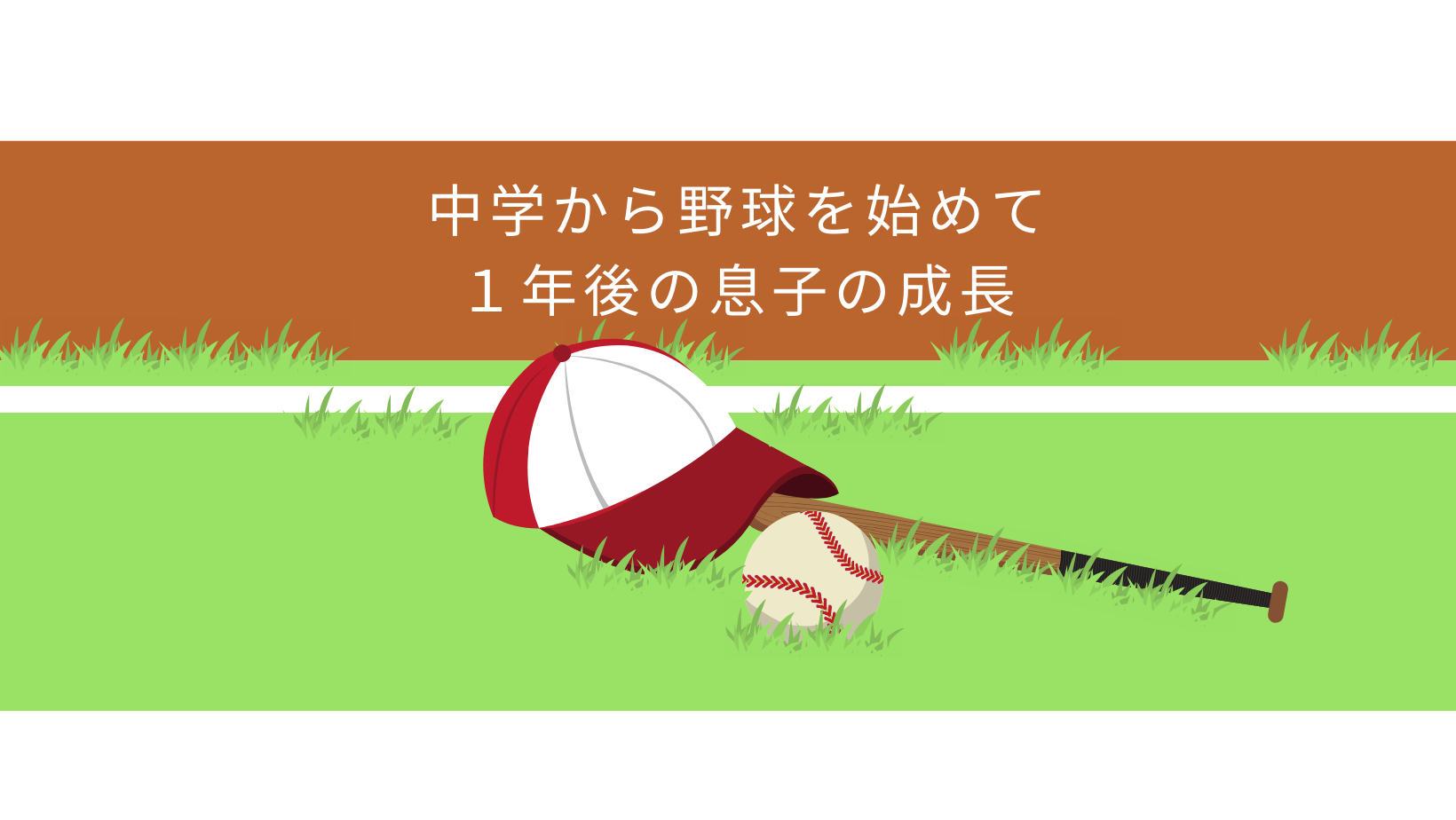小学1年生の娘の半年間の成長 ~ゆっくりマイペースな日々の記録~
.png)
ゆっくりマイペースな小学1年生の娘
こんにちは、kaoです。
下の子、小学校1年生の我が家の末っ子は、とってもマイペースでふんわりとした、自由な感じの女の子です。
家族全員が早生まれということもあり、小学校生活を心配していましたが、彼女のユニークさな個性が心地よい風を運んでくれようです。
娘の小学校生活が心配な3つの理由:苦手なポイント

「小学1年生の娘はあまり積極的に会話に参加せず、黙って自分がやりたいことを追求し、いつもニコニコしてふらふらと興味深そうなものを見つけたりしていました。
そのため、彼女自分の思考や感情を言葉で表現するのが苦手でした。
具体的に言うと、以下の3つの欠点が見られました:
- 聴力からの情報処理が苦手
- インプットはできるがアウトプットが苦手(言葉で表現すること)
- 学ぶことが苦手なこと
これらの課題に解決し、彼女がより豊かなコミュニケーションや学習経験を得られるようにサポートしていくことが重要です。
小学校生活の6ヶ月を経て、娘が以下のように苦手と共存できるようになっていました。
- 聴力からの情報処理が苦手: 聴力からの情報収集が苦手は友達を作って、困ったときに助けてもらう
- インプットはできるがアウトプットが苦手(言葉で表現すること):インプットはできるがアウトプットが苦手な場合、理由を添えて質問にじっくり練習を行います。
- 学習することが苦手: 学習することが苦手は学研にお友達と通って毎日宿題をし学習習慣を身に着ける
聴力からの情報収集が苦手は友達を作って、困ったときに助けてもらう。

入学当初、担任の先生によれば、慣れない小学校生活で先生の話が理解できず、涙しそうになる場面がよく見られました。
「娘ちゃん、こっちに並ぶんだよ、おいで。」と声をかけてくれて、何度も助けてくれたおかげで、彼女は現在も困っているときにその友達に助けられています。
保育園の頃から友達に恵まれ、困っているときに助けてもらうことで前を向いて進むことができます。
例えば、「○○が分からないけど、教えて。」 といった具体的な内容を口頭で伝えることができ、これが彼女にとっての聴力からの情報処理能力を向上させるための第一歩となりましたしました。
さらに、友達が必要なときに助けてもらった経験から、友達作りが大切なことを学ぶことができました。
インプットはできるがアウトプットが苦手な場合、理由を添えて質問にじっくり答える練習を行います
娘ちゃん、今日誰と何して遊んだの?
えーっと、忘れちゃった!
保育園の頃は、今日の保育園での出来事を聞いても「忘れちゃった。」と言って、思い出して言葉にすることを嫌がり、あまりにも話しませんでした。
しかし、小学生になると環境が変わって、お友達との交流が増えたことが影響しているのか、「今日小学校でね、○○ちゃんとね、○○して遊んだんだ。」など、積極的に面白い事を話せるようになりました。
さらに、男の子の同級生との関わりには最初は否定的でしたが、小学生になってから時間が経つと、国語の授業で教えてもらったことや出来事に理由を添えたり、自分の考えを言えるようになりました。
これらの変化は、成長とともにコミュニケーション能力や自己表現力が向上していることを示しています。
例えば、
ママ、今日ね○○くんとドッチビーしたよ!
そうなんだ。楽しそうだね。
それでね、○○くんが○○っていった事がすごくおもしろかったんだよ!
ママもおもしろいって思わない?
本当、○○君面白いこと言うね。
このように、男の子と遊んだことを楽しそうに話せるようになり、同級生の男の子も楽しく遊べるようになりました。
口から言葉で表現することで、インプットしたことを頭で整理し、人に話すことの面白さに下の子本人が気づくようになり、会話が増えました。
アウトプットが苦手だった心配事は学習面の心配事の解消にも繋がると思います。
困ったときに友達に困ったことを伝えて助けてもらえるから、自分の気持ちを言葉で表現できるようになりました。
教科書や本などから得た言語を口から言葉で人に伝えると伝わるという行動ができるようになりました。
学習することが苦手は塾にお友達と通って毎日宿題をし学習習慣を身に着ける
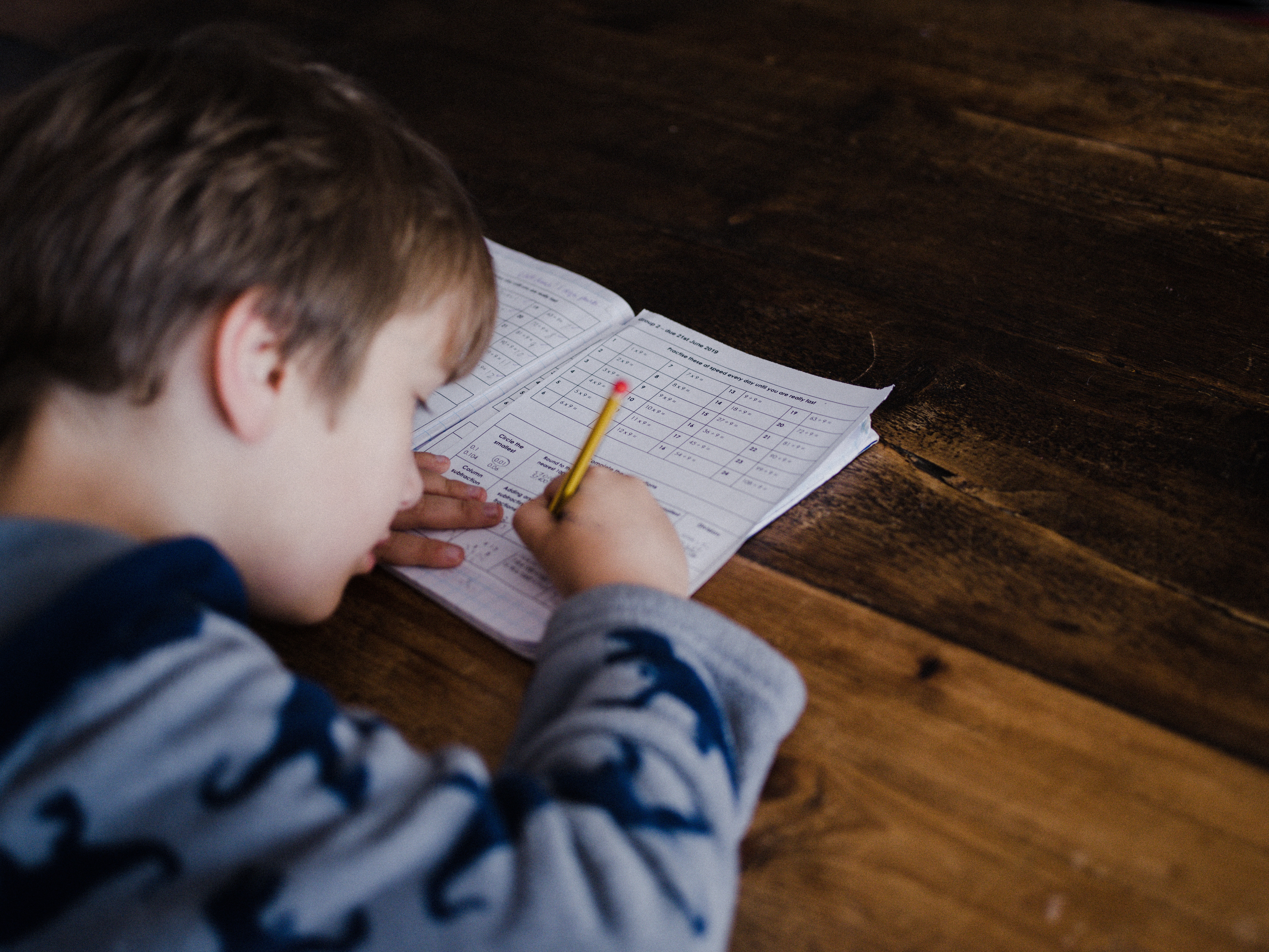
特に、聴力からの情報収集が苦手で、授業中に先生の口頭説明が理解できるのか、質問に答えられるのかという不安がありました。
テストでドラえもんに出てくるのび太君のような点数を取るのではないか?とはじめは考えていました。
この不安に対処するために、保育園の年長からベネッセさんのこどもちゃれんじに入会しました。
最初は楽しそうに居ましたが、一年生になると難しい問題に対して否定的な発言が増え、チャレンジ一年生を退会しました。
その後、学研教室を見つけ、先生に相談した結果、学研教室に入会しました。
この教室では個々の理解度に合わせて学習が進められ、娘が適していると判断しました。
通い始めると、友達が通っている影響か、嫌がらずに通えるようになり、「学研楽しい。」「勉強楽しくなってきた。」というポジティブな発言が聞けました。
また、学研教室では毎日の宿題プリントを自分で取り組む習慣が身につき、学校のテストでも100点をてれました。
毎日の学習習慣が彼女の自己管理力を向上させ、学習に対する自信を築く一助になったようです。
授業で学んだことを母に説明することで、その内容が記憶に残るようになりました
ママ、今日小学校でね、引き算のやり方を教えてもらったよ。
そうなんだ、ママにも教えてよ。
いいよ!じゃ2ひく1はどうやってやるかというと、式はこう書いて、答えはこうなるの!
娘ちゃんすごいじゃん!引き算をマスターしたんだね。
学童からの帰り道や夕食の時間など、学習した内容を会話の中で教えられるようになりました。
このような会話の中で、親の私にとっても彼女の理解度がどの程度かが理解できるようになりました。
教えられないことがあれば、それが理解できてない可能性があるかもしれない、と考え、逆に質問したりすることもあります。
また、口頭や書いて説明した内容を時間を経ってからもう一度問題を出すことで、彼女が間違いを少なくしていることがわかりました。
この何気ない会話が、娘本人が学んだことをより確実に記憶に定着させている手助けになっているようです。
翌日の準備が、自分でできるようになりました。
ママ、明日の時間割はごはん食べてから8時にやる。
おー、いいね!じゃ8時に一緒にやろう。
入学直後は、私の方から明日の準備をするように促していました。
このままでは本人自らが翌日の準備を行っていけるようになりません。
そこで、「じゃ、何時に明日の時間割の準備をする?」と声掛けし、娘自身で準備時間を決めさせて、その時間に必ず準備をすることを繰り返しました。
同時に時計も読めるようになり、日々の積み重ねと習慣が彼女に自ら明日の準備をするを育んできました。
小学校入学時の不安は、入学後に少しずつ解消されていきました。

小学校入学時の不安が解消され、それに伴い娘自身も成長してきました。
親は子供の行動を見守り、子供の話に傾聴し、寄り添いながら成長を感じることができます。
小学校一年生の娘が入学後半年でできるようになった事
- 口頭での説明の聞き取りが難しかった場合や困ったときは、お友達に助けを求めて不明点を解決できるようになりました。
- 自分が学んだ内容を頭で整理し、親にアウトプットできるようになりました。
- アウトプットすることで記憶が定着するようになりました。
- 学研教室への入会や仲の良い友達との学習が、勉強を楽しいと感じさせる取り組みとなり、毎日の学習が習慣になりました。
- 一人で小学校の準備ができるようになりました。
- テストで100点が取れるようになり、自己肯定感が向上しました。
まだまだ成長できる可能性がありますが、小学生になってかなり大きく成長したなぁと感じています。
これからも娘の成長をとても楽しみにしています。