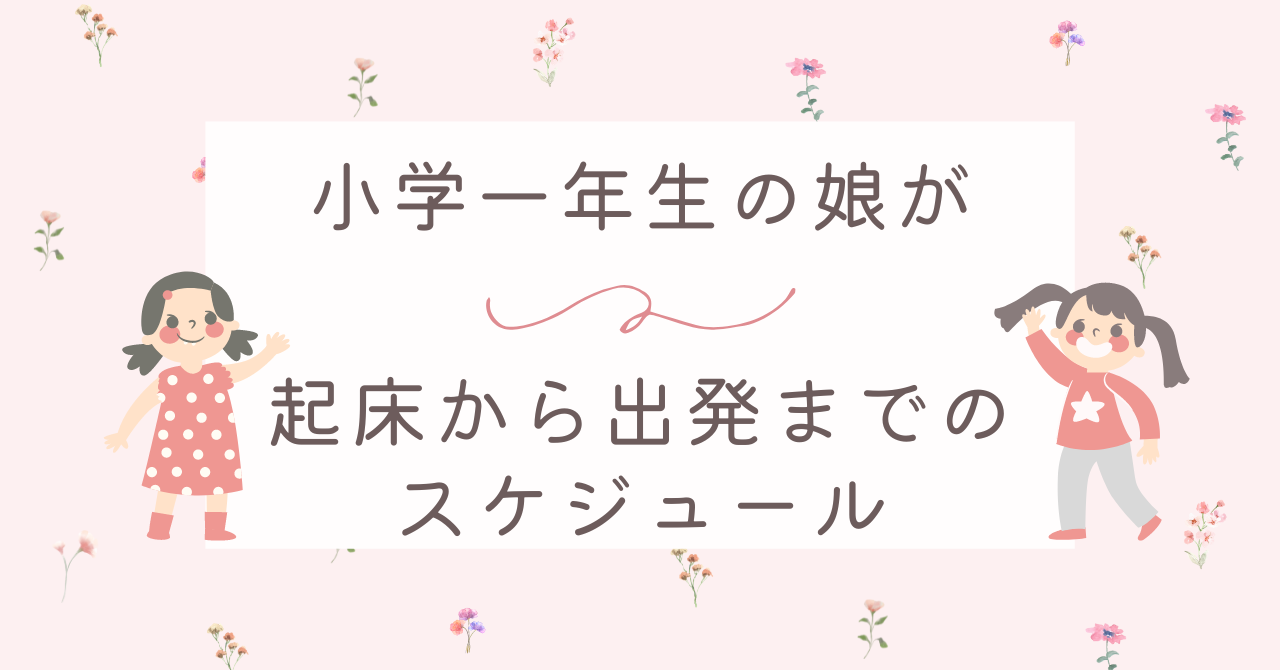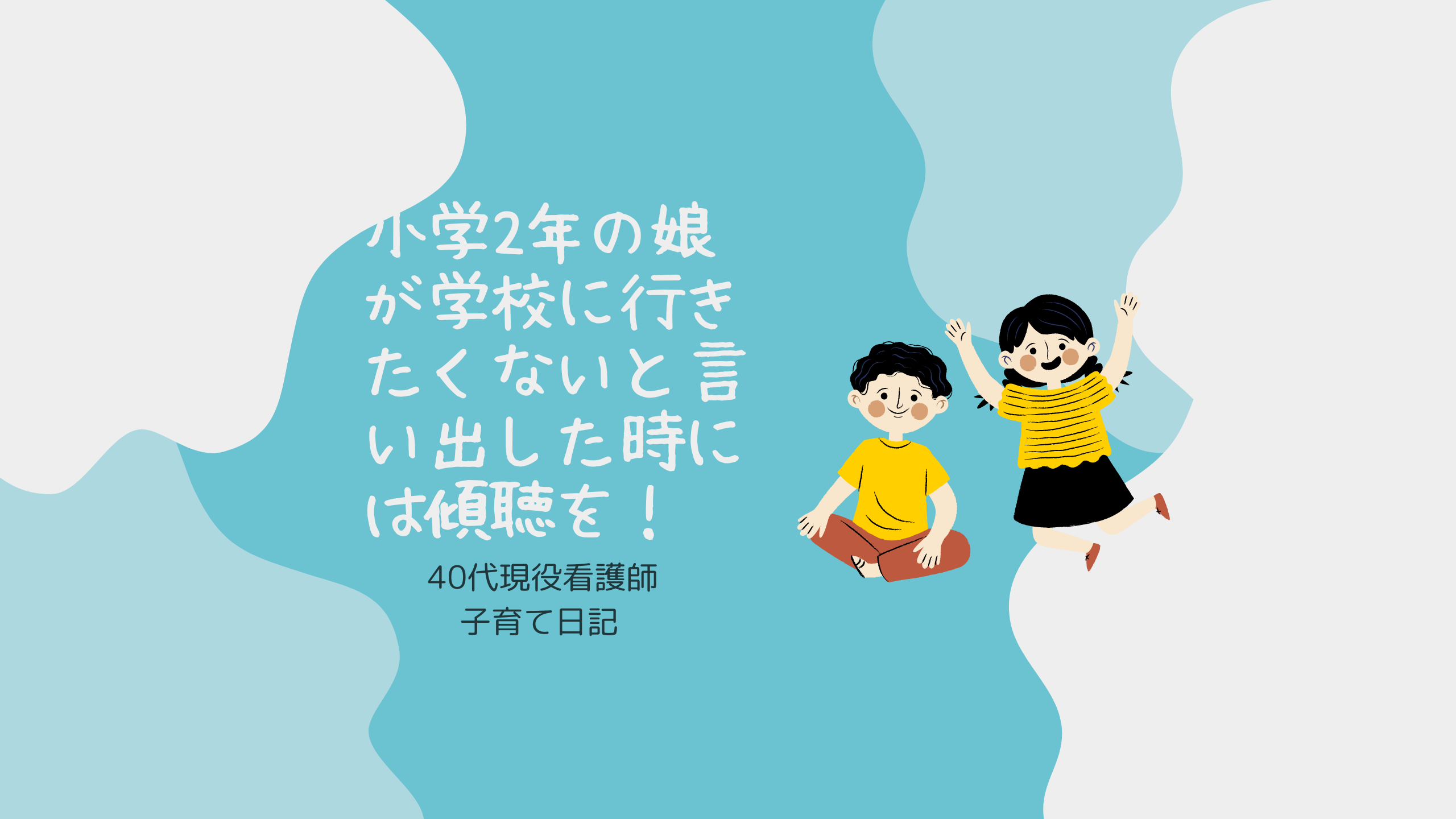小1の壁を乗り越える ~兄妹共の民間学童保育へ放課後、長期休み通う場合~

うちの子達、保育園に通うの3月31日で終わっちゃうね。
4月1日から保育園にいけないの私が不安だわ。
一人目だし、イメージつかないな。
その不安な気持ち、わかるなぁ。
うちのお兄ちゃんの時も不安しかなかったよ。
でも、新しい環境には子供はすぐなれるし、4月1日以降に放課後や長期休みの時に過ごす場所を決めておけば安心だよ。
そうなんだね。
是非、知りたいなぁ。
こんにちは!
子育てしながら看護師をしているkaoです。
「小1の壁を乗り越える」に焦点を当ててお話していきたいと思います。
小学1年生の娘が現在、放課後に民間の学童へ行き、習い事のヒップホップダンスや体操教室に参加しながら、小1の壁を乗り越える課題に立ち向かった経験を共有します。
小学6年生の息子も、小学1年から2年生の2月まで同じ学童保育に通いました。
私たちの家族が学童保育への取り組みを通じてどのように成長し、困難を克服していったのか、その一端を垣間見ていただけることでしょう。
小1の壁とは?

小1の子供たちが直面する様々な課題や変化について。
具体的に言うと、学校生活や友達関係や学業への適応できるかということです。
その中で、保育園に通っていた子たちが直面するのが、小学校が夏休みや冬休み、春休みなどの長期休み時の過ごし方です。
下記のサイトは民間学童保育協会のホームページです。
ご参考にされてみてください。
小学校生活の平日の学校休みと長期休み

春休み(3月下旬から4月上旬にかけて)
夏休み(7月下旬から8月下旬もしくは8月一杯まで)
冬休み(12月下旬から1月上旬)
参観日や運動会や学習発表会などの振り替え休日や創立記念日、市政記念日等の学校の休日がたくさんあります。
よって、長期休み中の子供の居場所を決めておく必要があります。
我が家は子供達2人とも民間の学童保育で低学年のうちは過ごしました。
えっ、小学校のお休みこんなにあるの!
仕事どうしよう。
大丈夫だよ。保育園に在園中に卒園後に過ごす場所を決めていけばいいんだよ。年少さんの頃くらいから少しずつ、自宅から近い場所から色々調べて検討してみようね。
そっか、年少の頃から少しづつ調べていけば、仕事しながらでも準備出来るよね。
民間の学童は地域によっては年少の時点からリサーチして学童保育などの申し込みもできるところもあります。
大都市圏だと子供の数も多く、学童保育の申し込みが激戦区の場所もあり、子供が年少の頃からリサーチし、申し込む必要がある場合があります。
早めの行動をお勧めいたします。
学童保育への決断

我が家が子供たちを民間の学童保育に預けることを決めた理由は、小学校に付随している学童より民間の学童保育の方が子供たちが長期休み中も遠足やキャンプなどイベントがあり、習い事もできて飽きずに通えることに魅力を感じたからです。
民間の学童保育を利用するメリット
- 万が一残業になっても20時まで預けられる。(延長料金あり)
- インフルエンザで学級閉鎖時や悪天候時の学校休校時も預かってくれる。
- 夏休みや冬休みなど長期休暇時に公園やアイススケート、登山など公共交通機関を使って遠足に連れて行ってくれたり、毎日イベントをやって子供達を楽しませてくれる。(別途料金は発生しますが子供にとっては良い経験になります)
- おやつを提供してくれる。
- 基本昼食はお弁当持参ですが、当日朝9時までに申し込みすれば有料でケータリング弁当を注文できる。
- 習い事(ダンスやそろばん等)が同じ建物内で行われている場合もあり、習い事も学童中にできる。
民間の学童保育のデメリット
- 料金が高額
- 利用申し込みを子供が年少の時に申し込まなければならないときがある。
- 遠足などのイベントが多く、アイテムを準備しなければならないものもある。
料金はかかりますが、好条件のサービスがあったため、利用申し込みを子供が年少の時に申し込み、年長の2月くらいに利用契約の順番が来たため契約に行きました。
私たちの住んでいる地域は子供の数が多いため、民間の学童の申し込みが殺到するため、年少の時に申し込むことがあります。
それでもキャンセル待ちで待って二人とも入れました(笑)。
挑戦と成長の瞬間
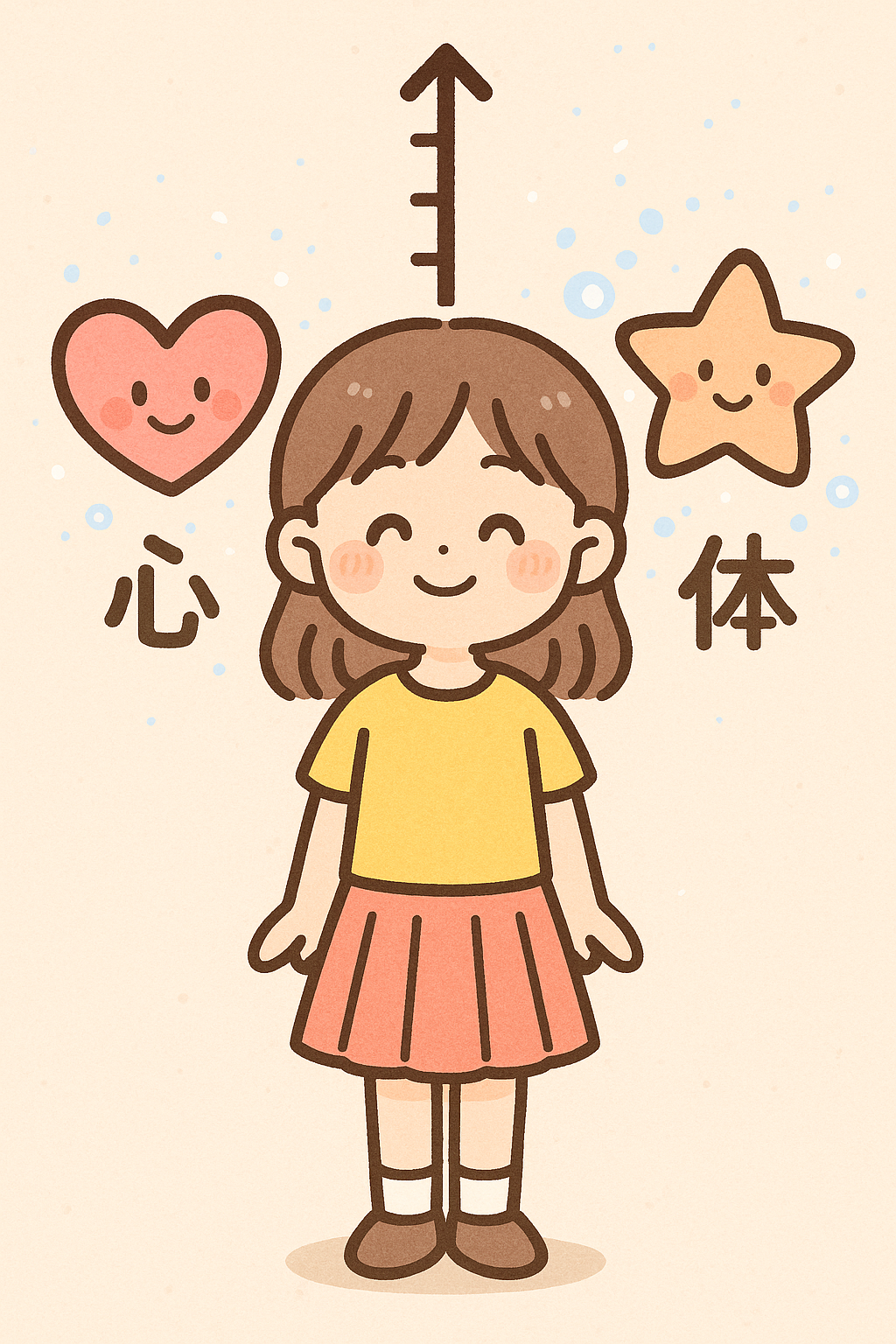
学童保育へ通う中での困難や克服した瞬間があります。
学童保育に通うことで、子供達の成長を促すメリットがありました。
民間の学童に入ることへの子供のメリット

- 同級生の違うクラスや違う小学校のお友達もできる
- 上級生や下級生のお友達もできて、楽しく遊ぶことができる。
- 電車やバスに乗って遠足に行くため、電車やバスの中でのマナーを覚えることができる。
- 体力が付く。
- 色々経験できる。
- お友達同士でのトラブルが起きても、先生が上手に介入して解決してくれる。
小学校の色々な学年のお友達ができ、関わることができます。
電車では座席は自分より小さい子やお年寄りに譲ること、リュックは前側でかるうこと、一列にならんで移動すること、Suicaを改札前までに準備すること等、身についていました。
先生方のかかわり方も上手で親子で信頼しています。
話も上手になり、お友達とのかかわり方も上手になり、日々成長を感じます。
上の息子は2年生の終わりごろに民間の学童をやめて、自宅帰る鍵っ子になり、下校後自宅から習い事へ行くことを練習して習得しました。
鍵っ子は鍵っ子で鍵をかけ忘れたり、鍵をひねりすぎてセコムさんが我が家に向かってこようとする等、色々失敗もありましたが、失敗も繰り返しながら鍵の管理を覚えました(笑)。
民間の学童もずっと通うわけではなく、低学年のうちのため、コストはかかりますが、保育園の延長と考えるようにしていました。
家族の結束力と成果

学童保育へ通うようになり、家族みんなで子供たちの準備を手伝いあい、子供達の成長へとつながっています。
長期休みでも学童保育は遠足などのイベントがあるため、朝の集合時間が早いです。
そのため、子供たちは早寝早起きの習慣が付きます。
親も早寝早起きの習慣が付き、お弁当作りの習慣が付きます。
夜は早く寝るために、手が空いている家族が明日の準備を子供と一緒に行います。
息子が中学生になると、お迎えは中学生以上が可能になり、息子に娘のお迎えに行ってもらったりします。
兄妹の協力や家族全体で育児の協力体制がつき、私も助かってます。
これからも家族と一緒に協力し合いながら共に成長していきたいです。
おわりに

小1の壁を乗り越えるプロセスが家族全体で協力し合い、家族の成長の機会となります。
保育園卒園後は環境がすべて変わり、子供たちと関わる人々も変わるため、親子で不安になります。
しかし、前もって準備したり、親子で練習してみたりして少しずつ慣れていくと、子供は体も心も脳も柔軟性があるため、すぐに慣れて覚えていきます。
すぐ忘れることもあるため、復習を忘れず、毎日毎日同じ行動をあきらめずに繰り返していれば、習慣になり、必ず覚えていきます。
成長を感じることができ、うれしく思うのですが、手が離れていく寂しさも感じることもあります。
これからも家族との大切な時間を大切にしながら、子供たちがさらに素晴らしい未来に向かって進んでいく事を期待しています。