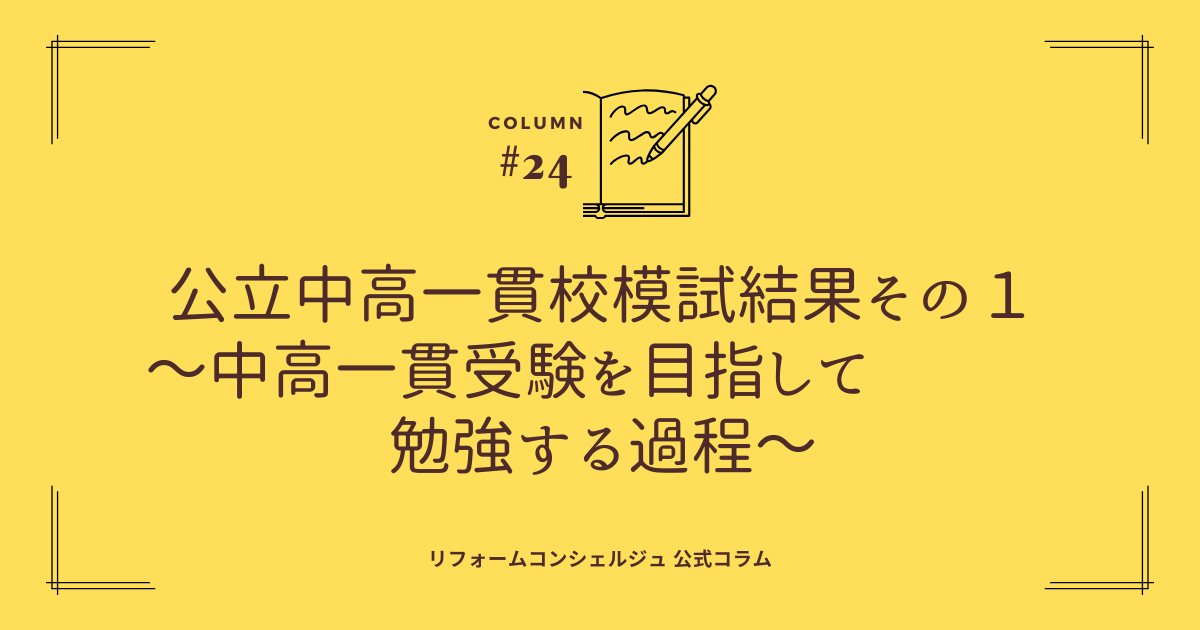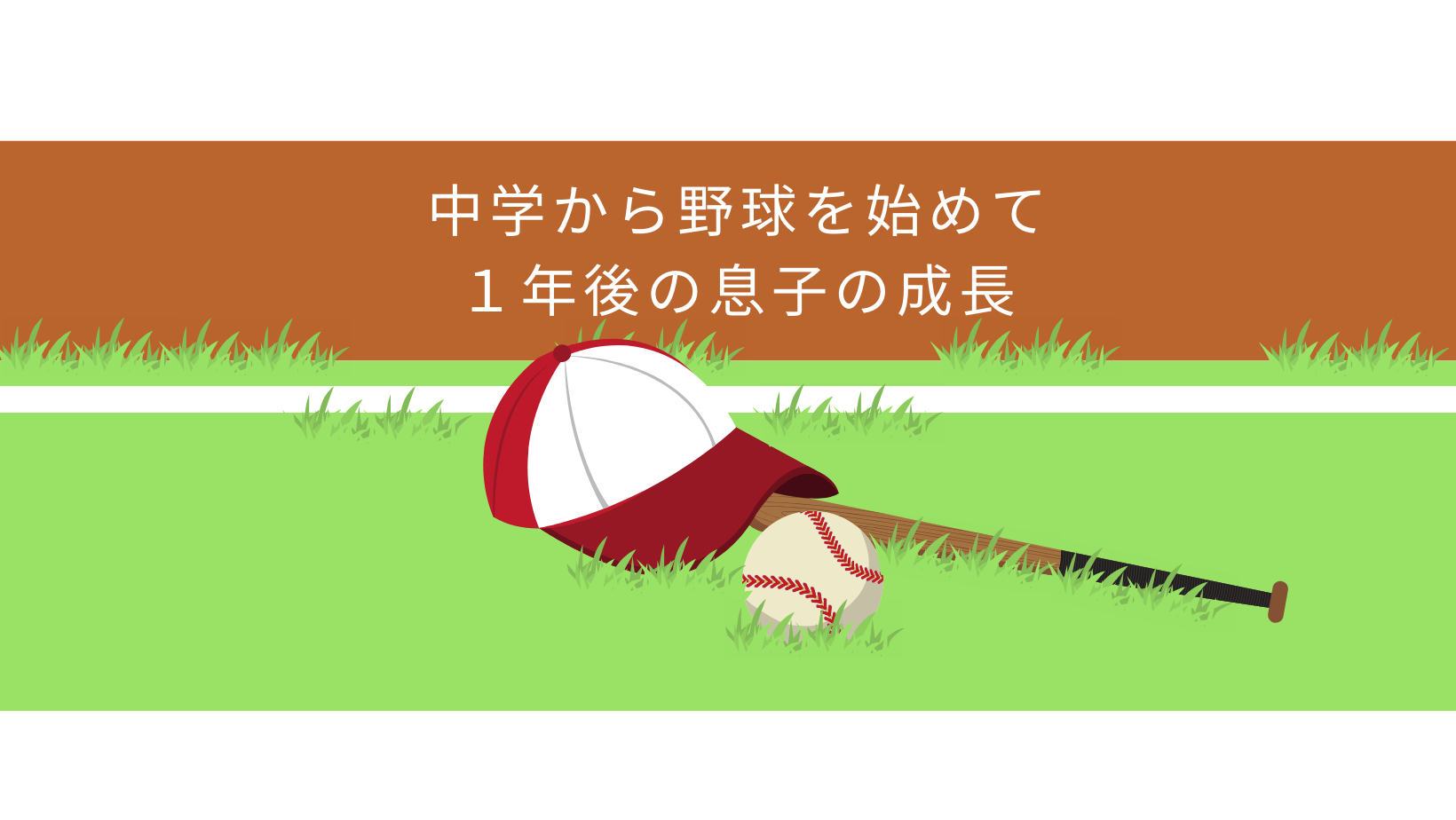小学3年生になった娘の成長と課題(ギャングエイジ女子との接し方について日々学ぶ)

この記事はアフィリエイト広告(プロモーション)を含んでいます。
こんにちは。kaoです。
あっという間に、娘が小学3年生になっていました。
私も歳をとるはずです(笑)。
今回は、小学3年生になった娘の成長とギャングエイジに突入した娘との関わり方の課題について紹介していきたいと思います。
1.小学3年生の娘の成長記録:自立心が芽生える瞬間

小学校3年生になった娘は、2年生の時と比べると小学校に行くことを楽しんでいます。
小学校に行くことが楽しくなった
小学校に行くことが楽しくなった理由としてはまず、1年生の時に同じクラスで仲が良かったお友達とまた同じクラスになったからです。
小学3年生になった娘の成長はたくさんあります。
毎日お友達とおしゃべりするのが楽しいようで、朝も進んで自分で学校の支度ができ、朝食後も茶碗を台所のシンクへ置きにきたり、片づけたりすることができるようになりました。
2つ目の理由として、担任の先生がベテランの優しい女性の先生になったことです。
3年生の担任の先生は、昨年度支援級の受け持ちをされていたそうで、経験もあり、娘を優しく見守ってくださいました。
よほどのことがない限り、担任の先生は怒らないことが娘の心に余裕を持たせてくれています。
娘も先生の話を真剣に聞き取り、先生に説明された通りに行動することができているとのことでした。
個人面談でも、2年生の時は問題山積みで担任の先生に支援級を勧められたこともありました。
しかし3年生の担任の先生からは、特に学校でも楽しそうに行動しているし、授業もついていけているので問題ないと言われました。
娘も担任の先生を信頼しており、担任の先生が大好きだと言っていました。
3年生になって楽しく学校に行くようになった3つ目の理由が、新しいお友達ができたことです。
新しくできたお友達は、登下校でおなじ道を通ることがわかり、学童へ行かない日はいつも一緒に登下校するようになりました。
気の合うお友達とワイワイお話ししながら教室でも登下校でも一緒で、いつも楽しそうに過ごしています。
学童保育へ行く日数を減らし、自宅で留守番ができたり、鍵の管理ができるようになった。

学童保育のお友達とも仲良く遊ぶのですが、毎日だと1年生からずっと同じメンバーのため遊びに飽きてしまいます。
学童のお友達以外お友達とも遊びたいと娘自身が思い始めたため、学童保育を週に2日にして、週3日は学校から直接自宅に帰宅し、クラスのお友達と遊ぶようにしています。
色々なお友達と遊ぶと、視野が広がって思考が偏らないかなと考えました。
学童へ行かずに直接自宅に帰宅するようになり、お陰で自宅の鍵の管理やお留守番ができるようになりました。
お留守番中は、夕方5時に学校と塾の宿題をやり、夜7時にタブレット学習で問題を解いています。
そのほかの時間は自由時間なので、お絵描きをしたり、YouTubeをみたり、ゲームをしたり、折り紙としたりなど、自分の好きなことをやって過ごしています。
自分で勉強する時間を決めて、勉強することを毎日習慣化することができました。
現在、娘がやっている学習塾とタブレット学習です。
よろしければご参考までに。
タブレット学習
毎日繰り返し問題を解くことで、小学校の授業も理解でき、テストも問題なく解けるようになりました。
時間管理とお友達と待ち合わせができるようになった

習い事がある日は、小学校から自宅へ帰宅後に時計を見ながら習い事に間に合うように自宅を出発する時間を娘が決めています。
学童保育の日数を減らした時には、時間管理ができるか心配で、出発時刻に電話をかけてアナウンスしたりもしましたが、現在では娘自身で時間管理をしてもらっています。
お友達と遊ぶお約束をしてくるときも、集合場所、集合時間、持ち物をお友達と確認して決めることもできるようになりました。
更に我が家にお友達が遊びに来るときは、事前に私や主人に遊びに来てもらっていいか確認ができるようになりました。
娘がお友達と自分たちで考えて決めたことを実行する楽しさを実感しているようで、なるべく色々な事を娘自身が決めていくようにしています。
もし、間違った選択をしていたとしても、命にかかわることでなければ間違ったことも勉強だと思って見守ることにしました。
たくさん失敗して、今度はどうやったら成功するかを自分の頭で考えられるようになると良いなと考えています。
2. ギャングエイジ突入!娘との向き合い方とコミュニケーション術

基本的には娘に色々と決めてもらうように声を掛けます。
例えば、
明日から夏休みで朝8時に学童保育に到着することになるけど、何時に起きる?
6時に起きる。
明日の夏休みから何時に家を出発する?
7時45分に出発する。
という風に翌日のスケジュールに関しては、前日に色々と本人と確認して、娘本人が自分で決めて準備できるように声をかけていきます。
当日の朝は前日決めた通りに実行していくだけ………。
なのですが、寝坊したりなど上手くいかない日もあります。
最悪寝坊しても良いように、余裕をもって起床時間は決めています。
よって、今まで遅刻したことは1度もありません。
親が時間管理の軸をしっかり持っていないと、子供に上手く管理させることができないと考えます。
私は時間管理が下手な方ですが、夫と一緒になって、娘が上手く時間管理できるよう、早め早めの行動と、余裕を持った時間管理ができるように指導しています。
朝食や当日着ていく服の選択は当日の娘の気分で決めています。
娘はごはんが好きなので、常に朝お米を炊くようにしています。
娘自身で決めたものは朝食もスムーズに食べますし、服もお気に入りの服を着て、気分よく朝の時間を過ごしています。
親は要となる時間をお知らせして、本人主導で行動できるように導けるコミュニケーション方法がお勧めです。
そのうち成長していけば、娘自身の脳内でスケジュールを立てて行動できるようになると思います。
そうなるまで見守って声掛けをサポートしていきたいと思います。
学校や学童からの帰宅後は、娘がその日の出来事を思いっきり話してくるため、ひたすら聞き続けます。
楽しかったことは、目をキラキラさせながら、嬉しそうに話してくれます。
話の腰を折らないように、ひたすら聞き続けて、満足するまで話し終えるのを待ちます。
話し終えた後、満足したのか一人で遊び始めたり、時には勉強し始めたりします。
急に切り替えるのでいつもビックリしますが、1,2年生の頃と比べると言葉の量が増えて、自分で言語化できるようになったことが、なによりの成長だと思い、いつも娘の話を聞くことが楽しみです。
3. 小3女子の心の成長と親としてのサポート

お友達と過ごす時間を楽しむようになってきて、親としてとても成長を感じます。
一人の時間も楽しんでおり、習い事の時も色々な友達と関わることで、それぞれの場面で会話やお友達と一緒に遊ぶことなどを楽しむことができるようになったことが2年生の時と比べて一番成長できたことだと感じます。
お友達に娘が提案したことをやりたくないと言われても、いじけずに違うことをを提案してみようという新たな発想を持つことができたことも、心の成長だと実感しています。
しかし、なるべく娘自身に色々と決めてもらうようにしていますが、やはり心配な面もあります。
色々と課題が山積みです。
1.知ったかぶりをしたり、素直に親のアドバイスを聴かない
色々と知識ややり方を紹介する場面があるのですが、「知ってる。」と言って知ったかぶってみたり、「今やろうとした。」などと親の私が言うことに対し、素直に物事を受け取れなくなってきています。
例えば、私が、こうやってみたらとやり方を提案すると、「私はこうやりたいの。」と自己主張強めに言い返されてしまします。
「ママはこう思うなぁ。」っと言い放ってその場を去ると、私の勧めたアドバイスを聴いていたりすることもあります。
こっそりアドバイスをして、放っておくのも一つの手かなと思いました(笑)。
2.うまくいかなかったことを人のせいにする
ある朝のやり取りなのです。
私は6時半にちゃんと起きたのに、ママが寝ていたからまた二度寝しちゃったの。だからいつもより支度が遅れたよ。
朝二度寝した事と、支度が遅れたことをママのせいにしないでくれる。
原因自分論だよ。
と言い返すと、何も言わずに小学校へ向かって出かけていきました。
二度寝を選択したのは娘自身です。
私も寝坊したのも確かに悪いですが………。
娘自身には原因他人論にして人のせいにしてほしくないです。
私自身も人のせいにしないです。
上手くいかなかったことも失敗したことも、色々自分で選択して行動した結果が上手くいかなかったことや失敗した事に繋がったのですから。
またやり方を変えて再度チャレンジしてみればよいのです。
娘にも人のせいにしないよう日々言い続けていきます。
自分の考えを持つことはとても良いことなのですが、失敗したことや上手くいかなかったことを人のせいにしたり、親や人からのアドバイスをスムーズに受け入れなくなってしまうことが見られるようになりました。
反抗期ってやつですね(笑)。
3.お友達の影響を受けやすい
お友達のやり方を真似てみたり、お友達のアドバイスはスムーズに受け入れていました。
やはりお友達と一緒に物事をやる方が楽しいようです。
お友達とおそろいのものを買ったりすることも楽しんでいます。
しかし、お友達が間違ったことをしていても、そのまま真似したり、受け入れてしまうところがあります。
善悪の判断をつけて自分で取捨選択をできるように教えていく必要があります。
日々、娘とコミュニケーションをとり、善悪の判断については一緒に考えて教えていく必要があります。
経験してみないとわからないことがたくさんあります。
たくさん行動して、たくさん失敗して、善悪の判断を少しずつ付けていってほしいです。
私も未だにたくさん失敗をするので、親子で学んでいきます。
4.スマホでLINEで友達とコミュニケーションをとるようになった

お留守番や一人で習い事に行くことになったため、困ったときの連絡用のためとGPS機能を活用するために、娘にスマホを持たせることにしました。
スマホを持つことで、位置情報が確認でき、習い事に行けているかを仕事中でも確認できるようになりました。
スマホを持たせたことで、学童保育の仲の良いお友達も皆スマホを持っており、お友達とLINE交換をしLINEでやり取りするようになりました。
返信が来たり、おうちにいてもお友達と電話ができ、会話することができる楽しさを知りました。
しかし、夜遅くまでLINEをやったしまうため、夜9時から朝7時までLINEやYouTubeが使えなくするように制限をかけました。
制限をかけたことで、スマホを夜間見れないようにし、夜9時30分までには寝れるようになりました。
娘本人からはスマホに制限を書けた当初は「みんなにおやすみメールを9時に送りたかったのに遅れなかった。」等と文句を言われてしまいました。
しかし、時間制限を書けたことは、娘の体や心の成長に必要な睡眠時間を8時間以上取ってほしいという理由であることを伝えると、納得してくれました。
際限なくやってしまうため、スマホの使用はブレーキをかけることもまだまだ親が管理しなければなりません。
今のところLINEの中でお友達とトラブルは起きていませんが、今後成長するにつれて、LINEの中身も目を光らせていきたいと思います。
4. 小学3年生のギャングエイジに向き合う親の心得
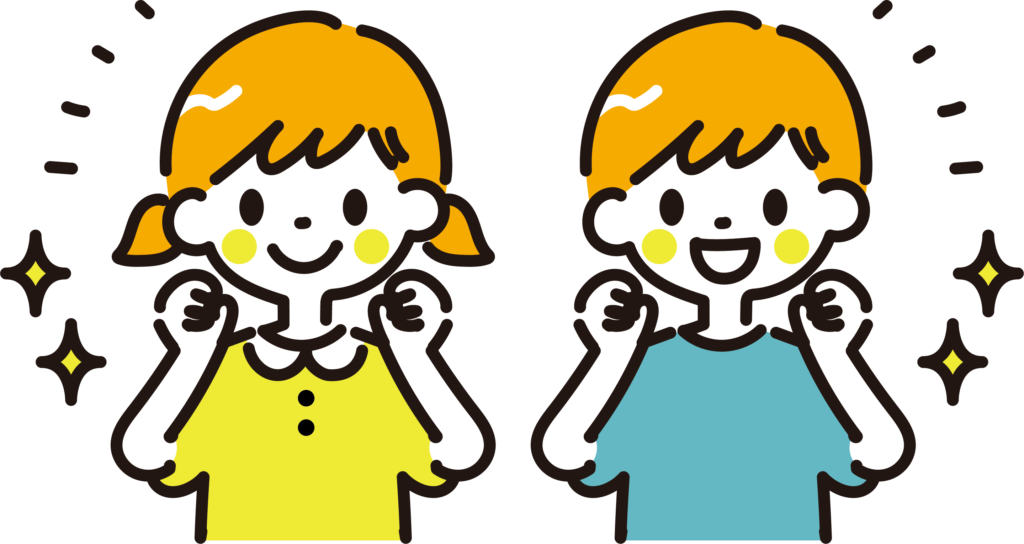
これからもっと親に反抗的な言動や態度が見られると思います。
しかし、娘の考えや思いを言語化してもらい、親の私の考えや思いも言語化して娘に伝えながらコミュニケーションをとっていきたいと思います。
そのためにも日ごろから、娘との会話を楽しみ、傾聴していきたいと思います。
人生にトラブルはつきものをテーマに、トラブルが起きても対処、フォローできるよう全力で娘をサポートしていきたいと思います。
5. 「娘が成長する瞬間:小3の自信と不安を見守る方法」

娘が3年生の一学期の前半の隣の席がやんちゃな男の子でした。
やんちゃな男の子は女子によくちょっかいをかけるので、女子から苦手意識を持たれていた印象でした。
しかし、娘はやんちゃな隣の男子と1年生の時から学童が一緒であり、彼の性格を理解していたため、やんちゃな男子が授業中おしゃべりしていると、「○○君、先生が説明してるから静かにしなよ。」などと言ってサラッと注意したり、やんちゃな男子が授業中分からないところを教えてあげたり等していたと聞き、お世話ができるようになったと娘の成長した瞬間を知ってしまいました。
2年生まではお友達に色々助けてもらっていた娘ですが、3年生になり友達が困っていたら教えてあげたり、助けてあげたり、注意してあげれるようになっていたのに、親として驚きでしたが、とても嬉しく思いました。
今後も娘の成長を楽しみに、見守っていきたいと思います。